足立区で天窓交換・撤去をするなら国土交通大臣認定事業者の屋根プロ110番にお任せください!
- 1級外壁・屋根調査士 関裕一
- 2022年6月29日
- 読了時間: 28分
更新日:2024年1月9日

江戸時代から日光街道の宿場町として栄え、今も北千住を中心に開発が進む足立区。
西には荒川・東には隅田川が流れ、区内には四季折々の景観が楽しめる公園も多くあり、自然にも恵まれています。
関東最大厄除大師として有名な西新井大師は、都内有数のパワースポットとして有名ですよね。参道には昔ながらのお土産店や食事処が並び、初詣や夏祭りには多くの人で賑わいます。
今回は、足立区とその近隣にお住まいの皆様に向けて、天窓のメリット、デメリットやメンテナンス、交換工事について解説いたします!
お家が明るくなり、開放感を感じられる天窓(トップライト)。
風通しがよくなる、光熱費の削減ができるといったメリットもあり、お住まいを建てる際にこだわった方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は天窓には以下のようなデメリットもあります。
・夏場は日差しが眩しい
・エアコンが効きにくい
・窓に当たる雨音が大きい
・掃除が難しい
実際に天窓のある空間で生活されると、思っていたよりも不便が多いため、お客様から「天窓を外したい」とご要望をいただくこともあります。
中には、「天窓から雨漏りしてしまった」とご相談をいただくケースもあります。
「新築のときは良かったのに…」と、天窓をつけたことを後悔されているお客様もいらっしゃいます。
しかし、天窓はデメリットだらけ、というわけではありません。
天窓のメリットとデメリットを両方理解して、必要なメンテナンスを知っていれば、そんなお悩みも解決することができます。
今回は、天窓が悩みの種になってしまわないよう、天窓が原因で起こるトラブルやメンテナンスについて詳しくご紹介します。
実際の交換工事、撤去工事の事例も掲載いたします。
ご自宅に天窓がある方はもちろん、今からご自宅に設置を考えている方も、ぜひ参考にしていただければと思います。
目 次
★足立区で天窓の交換・撤去工事なら国土交通大臣認定事業者の屋根プロ110番にご相談ください★
サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)の屋根プロ110番では、天窓のメンテナンスも含めた屋根リフォーム全般を承っております。
屋根・天窓の点検、お見積りは無料です。お家を建ててからしばらく経ち、「そろそろ点検をしたい」とお考えの方、特に気になる点はなくても「とりあえず一度見てほしい」という方も、お気軽にご相談ください!

お家を建てた当初は、皆さん「天窓をつけてよかった!」と思われていたのではないでしょうか。
風通しがいい・お家の中が明るい・空が見えるなど、天窓にはたくさんのメリットがあります。
にもかかわらず、いつの間にか「天窓を付けなければよかった…」と後悔してしまうのはなぜなのでしょうか。

実は、天窓は定期的なメンテナンスが必要です。
お住まいを建てるとき、将来的な屋根・外壁のメンテナンスはなんとなくイメージがあっても、天窓のメンテナンスの必要性を感じている方は多くありません。
新築を担当するハウスメーカーさんも、現場の施工業者ではないため、住宅の細かい箇所まで熟知しているわけではありません。
天窓のデメリットやメンテナンスについて詳しく知らない担当者もいます。

「天窓をつけたい」と考えている方は、メリットだけでなく、デメリットと今後のメンテナンスについても考慮しておくことが大切です。
メリットだけを見てしまうと、将来的に天窓を付けたことを後悔することにもつながってしまいます。
●一番のデメリットは「天窓の雨漏り」
実は、天窓は雨漏りしやすい箇所です。
当社でも、「天窓から雨漏りしている」とご相談をいただくケースが多くあります。

雨漏りの原因といえば、まず屋根を想像する方が多いかと思います。
一概に屋根といっても、棟や谷といった雨仕舞部分、外壁との取り合い部分、屋根材の隙間など、雨漏りが発生しやすい箇所は複数あります。
天窓も、屋根に穴を開けるのと同じですから、雨漏りの原因になりやすい箇所といえます。
通風性・採光性やデザインにまでこだわって付けた天窓ではあっても、雨漏りの原因になるなら、悩ましく感じてしまいますよね。
●困った!部品がなくメンテナンスができないケースも

いざメンテナンスをしようと思っても、取り付けた天窓のメーカーが既になくなっていて、部品が手に入らず修理ができない、ということもあります。
最盛期には、天窓のメーカーは10社ほどありましたが、現在は、日本ベルックスとリクシルの2社だけです。
(YKKAP、三協立山アルミからも天窓が販売されていますが、日本ベルックスのOEM製品となっています。)
部品の交換が必要でも、製造しているメーカー自体がなくなっていれば、新たな部品を調達することもできません。

天窓の耐用年数は、25~30年です。
日本には、この耐用年数を経過した天窓が100万窓もあると言われています。
通常、屋根葺き替えや屋根カバー工法、屋根塗装など屋根リフォームをおこなう際に、一緒に天窓のメンテナンスもするのが理想的です。ただ、交換部品がなければ修理もできません。
できる範囲で修繕をしてくれる屋根業者も存在しますが、天窓の不具合を完全に直せるわけではありません。
そのため、これまで耐用年数を過ぎた天窓は、雨漏りを防ぐためにも撤去しか選択肢はありませんでした。(建築基準法により採光量の問題で取り外しができない天窓もありますのでご注意ください)
しかし現在では、雨漏りのリスクを解決する方法として、撤去するか、交換するか選択することができます。
生産が中止してしまった天窓でも、比較的簡単に日本ベルックスの新しい天窓へと交換できます。


屋根材や外壁材と同じく、天窓にも耐用年数があります。
通常耐用年数は25年〜30年ですが、30年間メンテナンスをしなくて大丈夫、というわけではありません。
天窓には防水紙・水切り用の板金・固定用のビスなどが使用されています。残念ながら、これらの部材は30年ももちません。
部材が劣化すると、雨漏りなどの被害が発生する可能性が高くなります。
窓自体は問題なくても、部材が劣化し被害に繋がってしまうのです。
天窓そのものの耐用年数だけでなく、使用部材も含めてメンテナンスをすることが重要です。

主な天窓メーカーである日本ベルックスも、屋根リフォームの際に天窓をメンテナンスしなければ、天窓だけが耐用年数を超え、さまざまな不具合が生じると指摘しています。
一度雨漏りなど不具合が発生すると、工事の手間はもちろん、費用もかかってきます。
ですので、屋根塗装や葺き替えなどの屋根リフォームと同時に天窓のメンテナンスをすることが最適です。
天窓も屋根の一部と考え、屋根の修繕やリフォーム時期=天窓のメンテナンス時期と考えていただければと思います。

●耐用年数を超えた天窓のリスク「雨漏り」

耐用年数を超えた天窓の一番のリスクは「雨漏り」です。
突然の天窓からの雨漏りを、ほんの少しだから、時々だからと放置しておくのは危険です。
雨漏りの放置は、お家全体の寿命を短くしてしまうので、被害に気付いた時点での対処が重要です。
なぜ天窓から雨漏りが発生するのか、原因を見てみましょう。

天窓は、窓の周りをゴムパッキンでぐるっと囲んでいます。
このゴムパッキンは、窓と窓枠との隙間を埋めることで雨水の侵入を防ぐ役割があります。
しかしゴムパッキンは、太陽熱や紫外線、風雨によって徐々に劣化していきます。
劣化したゴムは硬化して、次第に亀裂が起こり割れが発生、窓と窓枠に隙間が生じます。
この隙間から雨水が浸入し、雨漏りを引き起こします。
ゴムパッキンの寿命は約10年です。そのため、設置から10年を超えた天窓はメンテナンスが必要になってきます。

天窓付近はゴミがたまりやすいのも、雨漏りの原因になります。
天窓には、屋根から流れ落ちてくる雨水を排水するため、水切り板金が設置されています。
そのため、通常であれば水切り板金・防水紙の内部に雨水が入り込むことはありません。
しかし、水切り板金の金具・接している屋根材の下などに落ち葉やゴミが溜まると、水が下に流れるのを遮ってしまいます。流れが止まった雨水は水切り板金の金具の内側に逆流します。
この状況が数年続くことで雨水が防水紙まで貫通し、雨漏りが発生してしまいます。
たまってしまうゴミは、風や鳥が運んできます。自然の現象は避けられませんので、定期的なメンテナンスが重要になってきます。

防水性能を高めるため、天窓は様々な部材によって設置されています。
・雨水の排水させる水切り板金の金具
・凹凸のある屋根材(瓦屋根など)に天窓を設置する際に使用されるエプロン(防水材)
・固定するためのビス
このような部材の劣化によって、雨漏りが発生することもあります。
・水切り板金の金具が、経年劣化のためサビついて割れてしまった
・ビスが外れて穴が開いた
・ビスが浮いて穴が露出した状態になった
・エプロンが破けた
天窓自体の耐用年数は30年といわれていますが、部材のメンテナンスは必要ということをご理解いただければと思います。

●天窓からの雨漏り!すぐにできる応急処置について

雨漏りは突然起こるもの。どうすればいいかと、不安に思われるかと思います。
そこで、万が一天窓から雨漏りした際の応急処置をご紹介します。
天窓は屋根にありますから、もちろん手は届きません。
ご自身で屋根に登り確認することは非常に危険です。絶対におやめください。
まず、落ちてくる雨水で室内の床材が痛まないように、雨水を受けるためのバケツを用意してください。
さらに、バケツに落ちた水滴の飛び跳ねを防ぐために、バケツの周囲は新聞紙やラップを敷いて、床を保護してください。
バケツ中に雑巾を敷いておくとバケツの水はねを防ぐことができ、さらに効果的です。
この応急処置をしていただいた上で、なるべく早く業者にご相談ください。

●新築から15年程度経過した住宅
新築から15年経ったら、天窓のメンテナンスの時期です。
天窓だけでなく屋根全体が劣化し、メンテナンスが必要な時期でもあります。
ここでしっかり点検・メンテナンスをしておくことで、雨漏りの発生リスクを抑えることができます。
・屋根材の劣化による防水力の低下→新しい防水紙の設置

・天窓の設置に使用したビスの浮き→シーリングで塞ぐ

・窓枠のシーリングの劣化→打ち直し

●新築から25~35年程度経過した住宅
新築から25年ほど経つと、屋根も天窓も寿命が近づいています。
同様に防水シートや下地も劣化している可能性があります。
天窓そのものの交換、もしくは撤去をする時期です。
屋根部材・天窓の寿命


定期的なメンテナンスをしてきた天窓も、25年〜30年ほどで耐用年数を迎えます。
天窓を交換するか撤去するか、どちらがいいか迷われる方も多くいらっしゃいます。
そこで、ここからは、交換・撤去それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
●天窓を交換するメリット・デメリット

天窓を交換すれば、これまで通り採光性・通風性・デザインに優れたお住まいで過ごすことができます。
また、最近の天窓は機能も向上しているので、選ぶ天窓によっては、以前よりもよりメリットを感じることができます。
・曇りにくく、汚れがつきにくいガラスを使用
・飛散防止の合わせガラス、網入りガラス
・日差しを71%カットするLow-Eガラス
・ガラスシール、内部結露保証20年つき
・雨水浸入・水切り保証10年つき
・ブラインド・電装品保証3年つき



機能性の高い天窓の中でも、Low-Eガラスは人気があります。Low-EとはLow Emissivityの略で、低放射のことです。
太陽光にも含まれる赤外線は、いったん物質に吸収された後、再放射されるという性質を持っています。
Low-Eガラスは、表面に金属のコーティングを施しており、太陽の光を反射し、再放射を抑えます。
結果、室内の温度の上昇を防ぐことができます。
また、コーティングはほぼ透明で目立たず、視界の妨げにもなりません。

天窓を交換すると、今後も定期的なメンテナンスが必要になります。
現在販売されている天窓は耐久性も向上し、以前より長持ちするものがほとんどです。
ですが、やはり定期的なメンテナンスは必要ですので、少し面倒に感じるかもしれません。
継続的なメンテナンスの必要性や、かかる費用なども事前に考慮しておくといいですよ。

●天窓を撤去するメリット・デメリット

天窓を撤去すれば、天窓からの雨漏りリスクがなくなります。
もちろん、今後のメンテナンスも必要ありません。天窓のある家にこだわりがない、メンテナンスが面倒、とお考えの方は、撤去を検討してみてはいかがでしょうか。
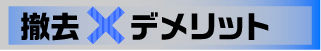
天窓を撤去すると、これまでの採光性、通風性はなくなります。
光を取り入れる天窓がなくなると、室内が暗く感じたり、雰囲気が変わってしまうこともあります。
また、建築基準法では最低限の採光量の確保が定められているため、撤去したくてもできない場合もあります。その場合は交換工事となりますので、ご注意ください。

交換にも撤去にもメリット、デメリットがある天窓ですが、皆さんのご健康、資産価値の維持という点から、多くの場合は交換工事をおすすめしております。

天窓のある家は自然の光が天井から降り注ぎ、外からのさわやかな空気が循環します。
皆様の健康にいい空間づくりに役立ちます。

また、この自然の光を利用して省エネすれば、光熱費の削減にも繋がります。
室内にいながら昼は空と雲、夜は月と星を眺めることができるのも、天窓ならではの魅力です。
ご自宅でゆったりと、快適に過ごすことができます。
現在の天窓は耐久性も向上しています。

もちろん、定期的なメンテナンスは必要です。天窓を撤去することも選択肢のひとつではありますが、天窓のある生活のメリットも多くあります。
天窓からの採光・通風がなくなってしまうと、予想以上に不便を感じるかもしれません。
天窓のことでお悩みでしたら、撤去だけでなく交換も含めたご提案をさせていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

●足場設置を有効活用しコストを削減できます
天窓の工事では屋根の上の作業になりますので、足場の設置は必須です。
しかし、足場設置には費用がかかります。
メンテナンス・工事の際には、できるだけ費用を抑えたいですよね。

そこで、当社では、複数の工事をまとめて行うことをお勧めしております。
天窓のメンテナンス以外にも、外壁塗装・屋根リフォームなどは足場が必要な工事です。
これらの工事をまとめて施工すれば、足場の設置が1回で済み、費用を抑えることができます。

大切なお家に快適に長く住み続けるためには、お住まいのあらゆる箇所において定期的なメンテナンスが必要です。
足場を設置する工事が必要になったら、同時に他の箇所のメンテナンス、リフォームもご検討ください。
●自然災害で被害を受けた天窓は火災保険が利用できます

天窓は、火災保険を利用すれば、自己負担がなく修理や交換ができる場合もあります。
火災保険は、「火事の被害に対しての保障」と思っていらっしゃる方が多いですが、実は火災保険は自然災害の被害に対しても適用されます。
例えば、「台風の被害による雨漏り」「ひょうが降って天窓のガラスが破損した」という場合も火災保険の対象です。
台風や暴風、豪雨、積雪、雹、落雷によって発生した被害は、火災保険で直すことができます。

内容によっては費用を負担することなく修理をすることができます。
サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)でも、火災保険を利用した工事を多く施工しております。
「うちの被害は火災保険が適用されるのか?」分からない場合は、お気軽にご相談ください。
当社では、保険の申請方法や窓口での対応などもサポートしています。

ただ、火災保険が利用できるのは、あくまで自然災害による被害の原状復旧工事です。
経年劣化が原因の場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
「火災保険で屋根のリフォームが可能です」という業者も存在しますが、多くの場合は経年劣化が原因ですので、保険は利用できません。
ご自身が加入されている保険の保障内容を一度確認してみてくださいね。
●天窓の種類と特徴
続いては、天窓の種類とそれぞれの機能についてご紹介します。
1981年創立の日本ベルックスは、国内で唯一の天窓(トップライト)の専門メーカーです。
サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)でも、天窓交換工事では日本ベルックスの天窓を使用しています。
日本ベルックス社の天窓は種類が豊富で、より快適に過ごせる機能性の高いものが揃っています。
日本ベルクス社の天窓ラインナップをご紹介しますので、天窓の交換をお考えの方は参考にしてくださいね。



電動タイプは、雨が降ったことを感知し、自動で天窓が閉まります。
最近は、突然局地的な豪雨が降ることも多いですよね。
突然の雨や、うっかり天窓を閉め忘れてしまったという場合でも、お部屋に雨が入り込む心配がありません。
網戸も付いているので、虫の侵入も防いでくれます。
リモコンで操作することもできます。


手動タイプは、ロッドを連結して窓を開閉します。
手動なので、配線を取り付ける必要がありません。
ロッドを回して天窓を開けた瞬間に風が通り抜ける心地よさを感じられます。
手元ハンドルでの操作も可能です。


フィックスタイプは、固定式のため窓は開閉しません。
通風性はありませんが、採光をメインにお考えの方、価格を抑えたい方におすすめです。
固定タイプは、開閉を行わないため、防水性が高いのがメリットです。
天窓を複数取り付ける場合などは、開閉タイプと組み合わせて設置するのもおすすめです。


ソーラータイプは、電源にソーラーパネルと蓄電池を内蔵しています。
VS電動タイプと同じく、雨を感知しすると自動で天窓が閉まります。
電動タイプは停電時に開閉ができなくなりますが、ソーラータイプは停電時も開閉することができます。



手の届く位置に天窓を設置するなら、ルーフウィンドウシリーズの手動タイプがおすすめです。
中軸回転式のため180度回転、お手入れも簡単です。


こちらは、業界初となる三層ガラスを採用した、寒冷地のお住まいにおすすめの天窓です。
三層ガラスで断熱性に優れており、室内に冷気が入り込むのを防ぎます。


こちらはGGUタイプをベースにした、排煙天窓です。
手動タイプと電動タイプがあり、電動タイプはリモコンで開閉できます。
非常時にはどちらも操作コードで開閉が可能です。



フラットシリーズは、陸屋根や緩勾配の屋根にも設置できる天窓です。0°~31°の勾配に設置でき、広々と空を眺めることができます。
戸建て住宅だけでなく、大型施設などにも広く利用されています。
●ガラスの種類を選ぶことができます
ご紹介したシリーズ全てにLow-E&汚れのつきにくいNeatの強化ガラスが採用されており、その中でも透明・網入り・型板網入りなどガラスの種類を選ぶことができます。
合わせガラスは、ガラスとガラスの間に樹脂を挟んで貼り合わせる構造のため、万が一ガラスが割れたときに破片が飛び散る心配がありません。
自転車のフロントウィンドウも、同様のつくりになっています。
※ルーフウインドウシリーズのGGL/GGU手動タイプは、合わせ透明+透明、または網入り+透明からお選びいただけます。
※ルーフウインドウシリーズのGGHタイプは網入り+透明のみの取り扱いです。
・合わせ透明+透明

透明ガラスと透明の組み合わせで、ガラスが割れたときに飛散しない安全設計です。
汚れがつきにくいNeatのガラスで、曇りにくく、天窓からの景色を楽しむことができます。
天窓からの景色を楽しみたいという方におすすめです。
・型板網入り+透明

ガラスの片面に網模様が入ったタイプです。
天窓の景色を楽しむことはできませんが、プライバシーの確保、強い日差しを遮り眩しさを軽減できるというメリットがあります。
・型板網入り+透明

割れたガラスの飛散を防ぐワイヤーが入ったタイプです。
ワイヤー入りガラスは火事の際に延焼を防ぐ役割もあり、防火設備としても有効です。
●ブラインドの取り付けも可能です
日本ベルックス社の天窓はブラインドの取り付けもできます。
ブラインドのラインナップをご紹介します。
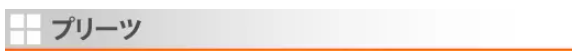
プリーツタイプは、直接室内に差し込む光を拡散させることで眩しさをカットします。
夏場の強い日差しを和らげ、やさしい光が広がる空間をつくります。
手動、電動タイプから選ぶことができます。

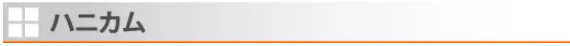
ハニカムは、遮光タイプのブラインドです。
朝の光もしっかりと遮るため、ベッドルームや、落ち着いた雰囲気のお部屋にしたいという方におすすめです。
手動、電動タイプから選ぶことができます。


アルミタイプのブラインドで、羽根の角度を変えることで光を調節することができます。
光量だけでなく、目線を遮る方向を変えることもでき、洗面所などに多く使われています。
手動タイプです。


ローラーは、GGLタイプとGGUタイプ専用のブラインドです。
直接室内に差し込む光を拡散させ、眩しさをカットします。通風性にも優れています。
手動タイプです。
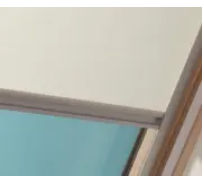

シェスタは、GGLタイプとGGUタイプ専用の遮光タイプのブラインドです。
遮光性に優れ、お部屋を真っ暗にすることもできます。
手動タイプです。

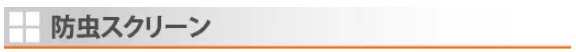
GGLタイプとGGUタイプ専用の防虫スクリーンです。
GGLタイプとGGUタイプの天窓は、回転式のため窓枠に網戸を付けることができません。こちらのスクリーンを設置することで、虫の侵入を防ぎます。
手動タイプです。


GGLタイプとGGUタイプ専用のブラインドで、室外に取り付けるタイプです。
Low-Eガラスと室内用ブラインドと併用することで、お部屋に入る日射熱を抑え、室内を快適に保ちます。

●足立区の天窓交換は「屋根プロ110番」にご相談ください!!

日本には、耐用年数である25年〜30年が過ぎた天窓がおよそ100万窓もあるといわれています。
お家を建ててから25年といえば、屋根の葺き替えなど、屋根全体のリフォームも考える時期でもあります。

サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)では、天窓の交換や撤去はもちろんのこと、屋根の葺き替えやカバー工事など、屋根全体のリフォームも承っております。
「そろそろ屋根のリフォームを考えている」「メンテナンスしたい」という方、「とりあえず点検だけでも…」とお考えの方も、お気軽にご相談ください。

点検は無料です。実際に屋根に登らせていただき、天窓や屋根の状態を詳しくお調べ致します。
しっかりと現状を把握し、皆様のお住まいに最適なリフォームをご提案いたします。
●天窓交換の事例
ここからは、天窓交換の施工事例をご紹介致します。
【実例①天窓交換と屋根カバー工法工事の同時施工】
・施工前、点検時の画像

お伺いしたのは、築21年のお住まいです。
天窓からは、写真のように、とても明るい日差しが差し込んでいます。
まだ雨漏りなどの不具合は発生していませんでしたが、天窓の耐用年数である25年が近づいています。
お客様も、これまで通り明るい部屋で過ごしたいとのご希望だったため、撤去ではなく、交換をご提案いたしました。

続いて屋根についてです。
使われていた屋根材はクボタ(現ケイミュー株式会社)のスレート屋根材「アーバニー」。
60センチ角ほどの屋根材でうろこ状に張られているのが特徴です。
この屋根材は、非常に割れやすいという特徴があります。
アーバニーは、ノンアスベスト屋根材の初期の商品で、当時は技術不足もあり、現在の屋根材よりも破損しやすいものが多く販売されていました。

一見すると厚手で頑丈に見えても、特徴的な形状であるため、残念ながら小さな衝撃でも破損してしまいます。
もともとアーバニーの耐用年数は15年ほどです。こちらのお住まいで21年使用していることもあり、ヒビ・欠け・割れなど損傷している箇所が見つかりました。
このような屋根の状態をご報告させていただいたところ、お客様も「劣化した屋根の元で過ごすのは不安。今後の雨漏りも心配」とのお話でした。
そのため、今回は天窓の交換と同時に、屋根カバー工事も同時に施工することとなりました。
・施工開始

サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)では、工事をはじめる前に必ず近隣の方へご挨拶に伺います。
工事中はどうしても業者の出入りや、作業音が発生します。
近隣の皆様とお客様が万が一トラブルにならないよう、工事の日程なども丁寧に説明いたします。
まず、足場を組み立てます。
足場設置の際も、どうしても作業音が発生します。屋根カバー工事中には、多少のホコリが出ることもあります。
サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)では、近隣の方にご迷惑をおかけしないよう、挨拶の徹底・ホコリ飛散防止用のメッシュシート取り付けなど、安全第一を心がけ工事を行います。
・天窓の交換

続いて、天窓を交換します。
既存の天窓を撤去し、日本ベルックスの固定型・フィックスタイプの天窓を新たに設置します。
天窓には、フィックスタイプと開閉式タイプがあります。
フィックスタイプは窓の開閉を行うことができませんが、開閉できるタイプよりも費用を抑えることができます。
窓が開閉しないため、雨漏りのリスクも軽減することができます。

「光を取り入れられればいい」という方にはフィックスタイプ、「天窓で風通しもよくしたい」、という方には開閉タイプがおすすめです。
目的に合わせてお選びください。

うっかり天窓を落下させてしまっては大変ですので、既存の天窓を慎重に外していきます。
天窓を外すと元の木枠が見えるので、劣化、腐食の状態を確認します。
続いて、新しい天窓の木枠を設置します。

今回の工事では、サイズが一致しましたので、そのまま取り付けることができました。
メ―カーが違うとサイズに誤差が生じる場合もあります。その際は、新しい天窓のサイズに合わせて開口部の工事も行います。
無料点検の際に、交換であればサイズが変わっても大丈夫か、天窓でメリットを感じている点など、お話をお聞かせいただければと思います。

養生が終わったら、新しい天窓を設置します。
お客様はこの天窓からの日差しをとても気に入っていらっしゃいました。
天窓は、通常の窓の3倍の採光効果があるといわれています。
日中は電気がなくても明るさを確保でき、節電、省エネも期待できます。

天窓用の防水紙を設置します。
雨漏りの主な原因は屋根ですが、特に天窓とその周りは、雨漏りの発生箇所になりやすい箇所です。
天窓交換工事の際は、防水紙(ルーフィング)にこだわり、天窓用の防水紙を敷いてしっかりと防水対策を行います。
サッシ周りにおいては、ほんの少し隙間があるだけで雨漏りの原因になってしまいますので、慎重に防水紙を敷いています。
※メーカーに発注した防水紙を使用しなければメーカー保証が付けられないケースがございますので、当社で確認いたします。

敷いた防水紙を立ち上げたら、天窓の交換工事は完了です。
日本ベルックス製の天窓は、遮熱・断熱性にも優れています。
太陽光が入りやすい南側に設置した場合でも、日射熱をコントロールし、室内の温度をいつでも快適に保ちます。

天窓による雨漏りなどのトラブルを防ぐには、10年ごとに天窓の防水や部品の点検・清掃といったメンテナンスをすることが大切です。
その後、天窓自体の耐用年数である25年~30年が経過したら、屋根リフォームと一緒に天窓の交換についても検討してくださいね。

天窓の交換が完了したら、屋根カバー工法工事を行います。
屋根カバー工法では、既存の屋根の上に、新しい屋根材を取り付けます。
古い屋根を撤去するよりも短期間で工事ができ、費用も抑えることができます。

まず、既存の棟板金・貫板の撤去作業を行います。
棟周辺の防水紙が劣化している場合は、雨漏りのリスクを防ぐため、しっかりと補修します。
金属屋根で懸念される遮音、断熱性能にも優れています。
防水紙は二次防水として雨水の浸入を防ぎます。今回は、遅延粘着型のタディスセルフという防水紙を使用しました。
防水紙は軒先から棟に向かって敷いていきます。
棟から敷いてしまうと、防水紙の継ぎ目が上になり、その継ぎ目から雨水が入り込んでしまう可能性があります。
このような施工ミスは、早期の雨漏りを招き、せっかくの工事が意味のないものになってしまいます。
工事のセオリーとしては当然のことですが、当社でもひとつひとつの作業の意味を理解し、丁寧に施工することを全員で心がけています。

防水紙を敷いたら、新しい屋根材を取り付けていきます。
今回は、耐久性に優れたIG工業のスーパーガルテクトフッ素という屋根材を使用しました。
スーパーガルテクトフッ素は、遮熱性鋼板と断熱材が一体となった屋根材です。変褐色やサビには20年、穴あきには25年のメーカー保証がついていて安心です。

外壁との接触部分は、隙間ができやすく、特に雨漏りが発生しやすい箇所でもあります。
防水紙をしっかりと立ち上げて敷き、下地を取り付け、板金でカバーしていきます。
その後、外壁と同色のシーリングで防水処理を行います。

最後に、棟板金を設置します。
貫板の取り付け、同質役物の棟板金でカバーしたあと、しっかりとビスで固定します。
板金の継ぎ目にも、隙間ができないようシーリングで防水処理を施します。

これで、屋根カバー工法工事が完了です。
今回使用した超高耐久ガルバは、従来のGL鋼板よりも約3倍長持ちします。
また、金属屋根は軽いことが特徴で屋根カバー工法に適しています。
同じ面積の屋根に設置した場合、金属屋根は瓦屋根の約10分の1、スレート屋根の約3分の1の重さです。
最後に、清掃・足場の解体をおこない、工事はすべて完了です。
【事例② 天窓の撤去工事】
・施工前、点検時の画像

雨漏りがするとのことでご相談をいただきました。
お話をお伺いすると、2年ほど前から、風向きや強さによって時々雨漏りするとのことでした。
屋根のメンテナンスは8年前に塗装工事を行ったとのことですが、築28年が経過した天窓についてはメンテナンスしていないとのことです。
天窓は、設置から10年ほどで窓枠のパッキンやシーリングの劣化が発生するおそれがあります。
実際に点検させていただくと、板金の浮きやビスの浮き、シーリングの劣化が確認されました。
今回は、お客様のご希望で撤去工事を行うことになりました。

既存の屋根材は、現在は製造されていないモニエル瓦が使用されていました。
天窓を撤去するためには、天窓とその周りの一部の屋根の葺き替えが必要となります。
既に製造が終了している屋根材を入手するのは通常難しいのですが、今回はなんとか入手することができました。
色違いではありますが、いずれは屋根全体のリフォームをしたいとのご希望もあり、今回の工事では入手した瓦を使用しました。

室内から見た天窓です。
天窓の周辺の壁紙が剥がれてしまっているのが確認できます。
雨水が落ちてくることはなかったそうですが、雨が降るたびに少しずつ壁紙が剥がれてきたとのお話でした。
天窓を撤去するときには室内からも穴を塞ぐ必要があります。天窓までの高さは7mほどあったため、作業のために室内にも足場を設置します。
穴を塞ぐ工事と同時に、剥がれてしまったクロスの貼り替えも行います。
天窓を取り外すために、まずは天窓周りの屋根材を撤去していきます。

屋根材を撤去したら、天窓を取り外します。
窓枠の木材の変色、雨漏りの原因となった雨水が入り込んだ跡も確認できました。
天窓を固定するためのビスや鉄部分にはサビも見られます。

このように劣化した天窓は、雨漏りの原因となってしまいます。
定期的なメンテナンスによって、雨漏りが発生する前に劣化に気付くことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
ただ、雨漏りが起きてからご相談をいただくケースが多いのが実情です。
天窓の撤去が完了したら、穴を塞ぐ作業に入ります。
木材で下地を組んだあと、野地板を被せ、ルーフィングを敷いていきます。
必要であれば、ブチルテープ等で補強も行います。
瓦を張るための瓦桟(かわらざん、瓦を引っ掛けるための木材のこと)、雨水が流れやすいようにキズリを設置していきます。

穴を塞いだら、野地板の上に防水紙を敷き、モニエル瓦を設置していきます。
外壁との立ち上がり部分は、雨漏りの原因になりやすい箇所です。雨仕舞の板金やシーリング材で、雨水が入り込まないようにしっかりと防水処置をおこないます。

今回は中古のモニエル瓦を使用し、既存の屋根と色が異なっていたため、事前に瓦を同色に塗装しておきました。
既存の屋根材と色を綺麗に揃えるためには全体的な屋根塗装も必要です。
今回は将来的に屋根全体のリフォームも予定しているとのことでしたので、全体の塗装は行いませんでした。

室内から見た天窓の撤去跡です。
室内側からは断熱材を入れ、ボードを張って、穴を塞いでいきます。
これだけでは見た目が浮いてしまうため、天井クロスの貼り替えも行いました。
剥がれかけた壁紙も貼り直しました。
クロスの貼り替えは面積にもよりますが、パテ補修や糊付けなど、乾燥に時間がかかるため終日の作業となることが多いです。
室内工事ではお客様のご在宅をお願いしておりますので、ご理解いただければと思います。
これで天窓の撤去工事は完了です。
最後に
今回は、天窓のメリットやデメリット、種類や実際の交換・撤去工事についてご紹介しました。
天窓は採光性、通風性に優れ暮らしを快適にしてくれますが、耐用年数を過ぎると雨漏りの原因になったり、トラブルが発生する場合もあります。
そのため、定期的なメンテナンスが重要です。屋根のリフォームの際、同時に点検をするのがおすすめです。他の工事と同時に行うことで、足場費用などを削減できます。
天窓の耐用年数は25~30年です。期限が近づいてきたら、交換か撤去を検討しましょう。それぞれにメリットとデメリットがありますので、天窓があることの良さと不便さを考えて選んでくださいね。
足立区で天窓についてお困りごとがございましたら、国土交通大臣認定事業者のサンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス)までお気軽にお問い合わせください。
今まさに雨漏りで困っている方だけでなく、「とりあえず一度点検だけしてほしい」という方、「今後、天窓の交換か撤去で悩んでいる」という方も、お気軽にご相談ください。
無料点検で状態を確認させていただき、屋根・天窓の状態や、お客様のご要望もお伺いしながら、最適な工事をご提案させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
必見!プロが教える外壁塗装の見積書の見方と選び方!

LINE公式アカウントからもご依頼頂けます!!
「著者情報」
関裕一
東京都足立区出身 1級外壁・屋根調査士・ドローンパイロット
サンセイホーム(株式会社三誠ホームサービス) 最高技術責任者
18歳から塗装職人として2.250件以上の施工に携わる。
塗装業界の歪んだ構造を塗り替えるべく、奇跡の「新時代塗装」倶楽部を主催している。
お家を長く保つアドバイスを、分かりやすくお伝えします。















.png)
.png)
.png)
.png)


Comments